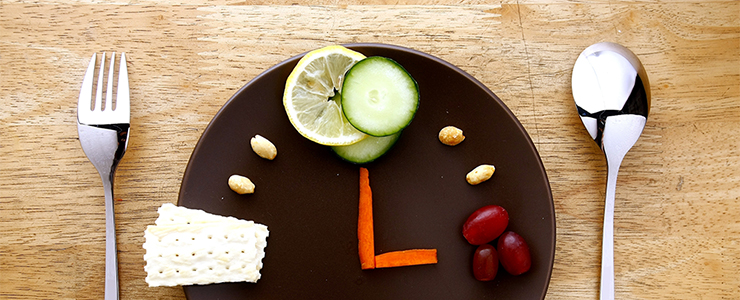SNS依存で心も体も危険に?やめられない理由と対策

「少しだけ…」と思ってSNSを見ていたのに、気づけば何時間も経っていた。
このような経験はありませんか?
SNSは便利で楽しい一方、使いすぎると心や体に負担をかけることがあります。
本記事では、SNSがやめられなくなる理由と心身への影響、そして上手に付き合うためのコツを解説します。
SNSがやめられなくなる理由

SNSは「やめよう」と思っても、ついのぞいてしまいがちです。この行動の背景には、脳の報酬系回路が関係しています。
自分の投稿に「いいね!」やコメントがつくと、脳内で「ドーパミン」という快感を感じるホルモン物質が分泌されます。
このドーパミンが「もっと見たい」「もっと反応が欲しい」という欲求を生み出すことにより、無意識のうちにSNSを繰り返しチェックしてしまうのです。
また、SNSは次々と新しい情報が流れてくるため、ギャンブルやゲームと同じように「次は何が出てくるだろう」という高揚感が高まります。これらが重なることで、SNSから離れにくくなり依存してしまうのです。
SNS依存がもたらす心身への影響

SNSには、最新ニュースやトレンドの情報収集や同じ趣味や価値観を持つ人とつながれるなどのメリットがあり、使うこと自体が悪いわけではありません。
しかし、依存すると少しずつ心や体に負担がたまっていくため注意しなければなりません。
取り残される不安感
SNSでは、友人や知人がリアルタイムで旅行やイベントなどの楽しい投稿をしていることがあります。特に、自分の気持ちが下降気味のときは、投稿とのギャップがより強く感じられ「自分だけが取り残されている」という感覚に陥りやすくなります。
また、「自分の投稿に反応がなかったらどうしよう」というプレッシャーもストレスの原因です。
「いいね!」やコメントが気になり何度も確認してしまうと、心が休まらずに不安感や焦りが強くなります。
睡眠の質の低下
スマホのブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑えるため、脳が昼間と同じように「覚醒状態」になってしまいます。さらに、SNSで刺激的な情報を見続けると、気持ちが高ぶって寝つきが悪くなることも。結果として、眠りが浅くなる、朝スッキリ起きられないといった症状が現れます。
睡眠不足が続くと、免疫力の低下や肌荒れ、日中の強い眠気や集中力の低下にもつながるため、心身の健康に大きな影響を与えます。
首や肩のコリ症状
SNSを見るときは、自然とスマホを覗き込む姿勢になります。この前傾姿勢が長時間続くと「スマホ首」と呼ばれる状態になり、首や肩に大きな負担がかかります。初期は軽いコリやだるさ程度ですが、悪化すると頭痛や腕のしびれなどが出ることも。
また、首や肩の筋肉が緊張すると血流が悪くなり、自律神経も乱れることで、めまいや耳鳴り、慢性的な疲労感といった全身の不調につながります。「ただの肩こり」と軽く考えず、日頃からストレッチや姿勢改善を意識することが大切です。
SNSと上手に付き合うコツ

SNSを完全にやめる必要はありませんので、以下のことを意識して利用してみましょう。
通知をオフにする
SNSアプリの通知音やバッジは、「見たい」という気持ちを刺激するため、まずは通知をオフにします。INEや電話など、本当に必要な連絡手段だけ通知を残すと良いでしょう。
「通知があるたびに見ない」という習慣がつくだけで、SNSに振り回されにくくなります。
時間を決めて使う
だらだらとSNSを見続けないためには、時間制限を設けることが有効です。タイマーを使って「休憩の30分だけ」などルールを決めましょう。あらかじめ制限を設けることで、後悔せずにSNSを楽しめます。
寝る1時間前はスマホを見ない
寝る前にSNSを見ると脳が興奮して寝つきにくいため、寝る1時間前はスマホをオフにするのがおすすめです。代わりにリラックスできる音楽や読書などを取り入れると、自然と睡眠の質が高まります。
オフラインで楽しめる趣味を持つ
SNSは「手持ち無沙汰でつい見てしまう」ということもあります。このようなときは、オフラインで楽しめる趣味を持つことが大切です。散歩やストレッチ、読書、料理、手芸など、自分が心からリラックスできることなら何でも構いません。
SNS以外の「心を満たす時間」が増えることで、自然とスマホから距離を取れるようになります。
まとめ
SNSは楽しく便利なツールですが、使いすぎると心や体に少しずつ負担がかかります。
「やめられない仕組み」を理解し、少しずつ使い方を工夫することが大切です。
無理に手放すのではなく、心地よい距離感を意識してSNSと付き合うことが、心身の健康を守る第一歩となります。