指定難病とは?わかりやすく解説

家族や自分自身が「指定難病」と診断されたとき、わからないことだらけで不安を感じることも多いのではないでしょうか。
本記事では、指定難病とは何のことなのか、受けられる支援はあるのかについて解説しています。
指定難病の定義とは?

指定難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づいて国が定める難病のうち、以下2つの要件を満たす病気が指定難病として認定されています。
患者数が本邦において一定の人数に達しないこと(患者数が人口の0.1%程度以下)
客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
指定難病に該当する疾患は、令和7年4月1日より348の疾患が認められます。また、対象となる疾病は継続的に見直されています。
難病の定義は、以下の4つです。
発病の機構(しくみ)が明らかでない
治療法が確立していない
希少な疾病
長期の療養を必要とする
がんや精神疾患などは、すでに調査や研究など対策がされているため、難病の対象にはなりません。
指定難病患者が受けられる経済的サポート
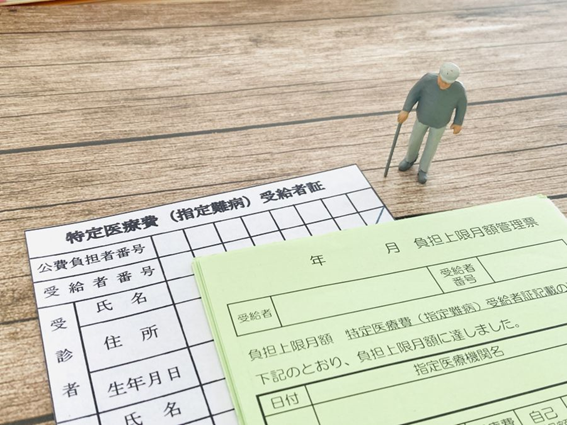
指定難病は、原因不明かつ治療法が確立しておらず、医療費が高額になりがちです。そのため、一定基準を満たしている患者の医療費の一部を助成する制度があります。
医療費の助成は、指定難病と診断を受け以下2つの認定基準に該当した場合、受けることができます。
重症度分類に照らして、症状の程度が一定以上
軽症高額該当(重症度分類を満たしていないが、月の医療費総額が33,330円を超える月が年に3月以上ある場合)
申請には、特定医療費(指定難病)受給者証・診断書・住民票・世帯の所得を確認する書類などが必要です。
手続きの詳細や不明なことは、病院のソーシャルワーカーや保健所、自治体の担当窓口で相談できます。
指定難病の診断を受けたら行うこと

指定難病と診断されたら、次のことを行いましょう。
主治医と相談する
診断後は、わからないことや不安を感じることが多くあると思いますので、主治医から病気の特徴や経過、治療法について詳しく説明を受けましょう。
また、少しでも疑問がある場合は遠慮なく質問してください。メモを取ったり、可能であれば家族と一緒に説明を聞いたりするのも良い方法です。
医療費助成の申請準備
指定難病と診断され一定の基準に当てはまる場合、医療費助成の対象となりますので、申請の準備を行いましょう。
受付窓口は、都道府県などによって異なります。必要書類など申請についての詳細は、居住している自治体の担当窓口(保健所や福祉事務所など)に確認してください。
信頼できる情報を集める
疾病の詳細な情報を集める場合、インターネットやSNSを使用することがあるかもしれません。しかし、これらには不確かな情報が含まれているケースもあります。
そのため、情報収集をする際には、厚生労働省や難病情報センターのウェブサイト、患者会の情報などを参考にして、正しい情報を収集するようにしましょう。
体調に合わせて
難病による体調は、日によって良くなったり悪くなったりする場合も多くあります。調子が悪いときには無理をせず、体調に合わせた生活リズムを作ることが大切です。
周りには気付いてもらえないこともあるため、必要に応じて職場や学校に説明したり配慮を依頼したりすることも検討しましょう。
まとめ
指定難病は決して一人で抱え込むべき問題ではありません。国や自治体による医療費助成制度があり、専門的な医療機関や相談窓口も整備されています。
診断を受けたばかりの頃は不安が大きいと思いますが、正確な情報を集め、適切な支援を受けることで、疾病と上手に付き合いながら生活している患者さんも多いです。
まずは主治医としっかり相談し、自治体の窓口で医療費助成の申請について相談してみましょう。









