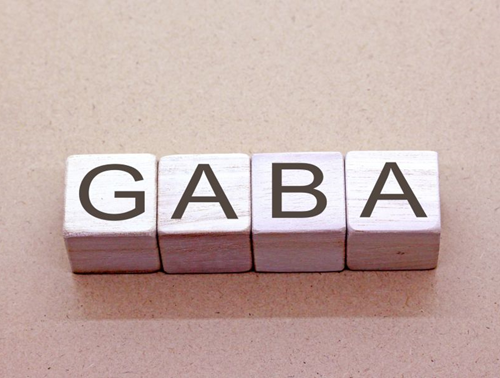食品添加物を過剰摂取すると体にどんな影響がある?

スーパーやコンビニで販売されている食品の多くには、「食品添加物」が使われています。近年では、「無添加」を謳う商品も増えており、「添加物=体に悪いもの」というイメージを持つ方も少なくないでしょう。
しかし、食品添加物には、私たちの生活を便利にする役割もあり、すべてが一概に悪いとは言えません。
本記事では、食品添加物とは何か、そのメリット・デメリット、そして過剰摂取による健康への影響について詳しく解説します。
食品添加物とは?

食品添加物とは、食品を加工したり保存したりするために使用される物質を指します。
例えば、保存料・甘味料・着色料・香料などが代表的な添加物です。
食品の品質を保ったり、味や見た目を良くしたりするために使用されており、日本では厚生労働省が安全性を評価したうえで使用が認められています。
つまり、適切な範囲で使われている限り、健康に影響を与えるリスクは非常に低いとされています。ただし、過剰摂取や偏った食生活が続くと、体に悪影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。
食品添加物のメリット・デメリット
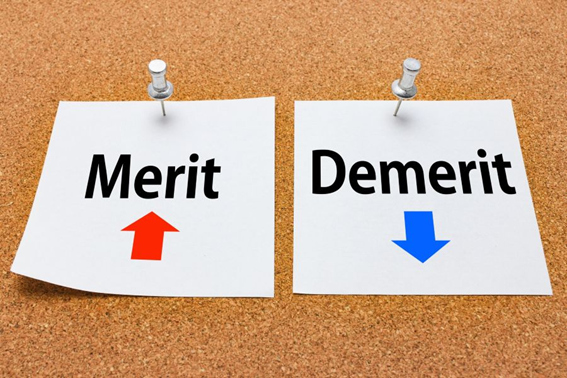
ここでは、食品添加物のメリット・デメリットについてそれぞれ解説していきます。
食品添加物のメリット
食品添加物の最大のメリットは、食品の安全性や保存性を高めることです。
例えば、保存料は腐敗を防ぎ、食中毒のリスクを減らします。酸化防止剤は、油脂の劣化を防いで味や香りを保ちます。
また、着色料や香料の使用は、見た目や香りを向上させ、食欲を刺激する効果があります。
さらに、加工食品の生産や流通をスムーズにし、コスト削減にもつながるため、より安価に入手できる食品が増えるという点もメリットです。
食品添加物のデメリット
食品添加物には、注意すべきデメリットもあります。最大の懸念は、過剰摂取による健康被害です。
例えば、発がん性が指摘されている「亜硝酸ナトリウム」や、動物実験で脳への影響が報告された「アスパルテーム」など、使用が認められていても摂取量には注意が必要な成分もあります。
また、化学物質に過敏な人は、少量の添加物でもアレルギーや体調不良を起こす場合があります。
さらに、人工的な香料や甘味料に慣れると、本来の食材の味を感じにくくなり、味覚が鈍くなるリスクも指摘されています。
食品添加物の過剰摂取による体への影響

日本では、「一日摂取許容量」が設けられており、これを超えないように設計された食品が販売されています。そのため、通常の食事をしている限り、過剰摂取になることは少ないとされています。
しかし、注意したいのは、加工食品や「超加工食品」に偏った食生活です。
超加工食品とは、自然の食材から大きくかけ離れた、工業的に強く加工された食品のことを指します。
食品添加物が多く使用されており、家庭では再現困難な方法で加工されているもので、スナック菓子、菓子パン、冷凍食品、インスタント麺などが該当します。
食品添加物の摂取で、特に問題視されるのが、複数の添加物を同時に摂取する「複合摂取」です。
単体での安全性は検証されているものの、組み合わせたときの影響はまだ十分に解明されていません。
また、添加物を多く含む食品は、糖分・塩分・脂質の過剰摂取につながりやすい傾向があり、肥満や糖尿病、メタボリックシンドロームといった生活習慣病のリスクが高まる恐れがあります。
この他、腸内フローラの乱れによる便秘・下痢など、消化器系への影響も報告されています。
まとめ
食品添加物は、現代の食生活に欠かせない存在であり、保存性や味の向上、食の安全性に貢献しています。一方で、過剰に摂取すれば健康リスクを高める要因にもなりかねません。
加工食品に偏った食生活は、知らないうちに添加物を多く摂取することになり、腸内環境の悪化やアレルギー、味覚障害など、さまざまな体の不調を引き起こすリスクがあります。
重要なのは、「完全に避ける」ことではなく、「適切な量を心がける」ことです。食品表示を確認する習慣をつけ、無添加または添加物の少ない商品を選ぶように意識してみましょう。自然の食材を中心に、バランスのとれた食生活を心がけることで、食品添加物と上手に付き合っていくことができます。