納豆は健康に効果がある?食べる注意点も解説

「納豆は体に良いと聞くけれど、どんな効果があるのかよくわからない」という人も多いのではないでしょうか?
本記事では、納豆は本当に健康に効果があるのか、食べるときに注意する点があるのかを解説していきます。
納豆の効果が気になっている人は、ぜひ参考に最後までお読みください。
納豆とは?

納豆は、蒸した大豆を納豆菌によって発行させた食品のことです。
納豆菌は、枯草菌(こそうきん)という細菌の一種で、畑や枯草、稲わらに存在しています。
人間に対する病原性がない安全な菌として知られており、煮た大豆に加えると発酵の過程でたんぱく質を分解し、納豆特有のにおいや粘り気が出ます。
納豆には、主に糸引き納豆と塩辛納豆(寺納豆)の2種類です。一般的に広く食べられているのは糸引き納豆で、納豆菌による発酵で糸を引くのが特徴的。
一方、塩辛納豆は、大豆と小麦と麹菌を塩水に浸けて発酵させた納豆のことをいいます。黒褐色で糸を引かず、塩辛く味噌のような風味で、調味料として使われることが特徴的です。
納豆に含まれる栄養素

納豆には以下のような栄養素が含まれています。
たんぱく質:筋肉や皮膚、髪の毛などの材料となります。ホルモンや酵素、免疫機能などの、体を調節する機能にも役立っています。
食物繊維:水溶性・不溶性のどちらの食物繊維が含まれ、腸内環境を整えて便秘を解消します。
ビタミンK2:骨にカルシウムが沈着するのを助けることで、効率よくカルシウムを吸収して骨の健康を維持します。
ナットウキナーゼ:血栓を溶かして、血液をサラサラにする効果があります。
大豆イソフラボン:女性ホルモンの「エストロゲン」に似た働きがあり、美肌の維持や更年期障害の緩和が期待できます。
ビタミンB群:水溶性のビタミンの一種で、エネルギ―代謝や疲労回復に役立ちます。
鉄分:貧血を予防します。体内で作ることのできないミネラルの一種で、食べ物から摂取するほかありません。
納豆は健康に効果があるのか

納豆に含まれる豊富な栄養素により、以下のような健康への効果があります。
腸内環境の改善:納豆菌は生きたまま腸内へと届くため、善玉菌を増やし悪玉菌を減らすことで腸内環境を整えます。
骨の健康維持:ビタミンK2は、骨にカルシウムが沈着するのを助け骨密度を高めることから、骨粗しょう症の予防効果が期待できます。
血液サラサラ効果:ナットウキナーゼは血栓を溶かし、血液をサラサラにする効果があります。血栓が原因で発症する脳梗塞や心筋梗塞などの予防ができます。
免疫力向上:納豆菌は免疫機能を増強させることがわかっており菌やウイルスなどから身を守る効果が期待できます。
美肌・美髪効果:納豆に含まれているビタミンB群は肌や髪の健康を維持します。また、女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンは、美肌や髪の毛の薄毛対策に効果的といわれています。
ダイエット効果:納豆は高たんぱく質で食物繊維も多く含まれているため、ダイエットにおすすめの食材です。
納豆を食べるときの注意点
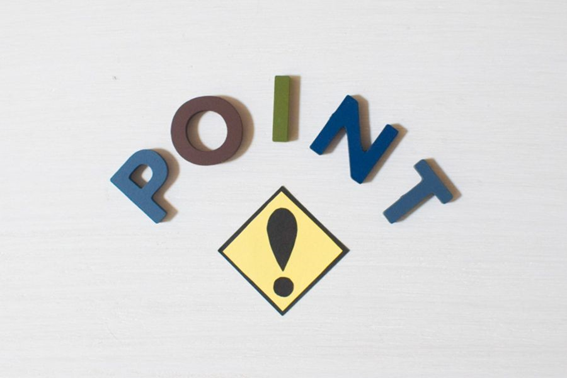
納豆は健康に良い食品ですが、食べるときの注意点がいくつかあります。
食べる量に注意する
薬との相互作用に注意する
アレルギーに注意する
それぞれ解説していきます。
食べる量に注意する
納豆はプリン体を多く含んでいるため、過剰摂取は痛風のリスクを高める可能性がありますので、1日1パックを目安に食べましょう。
薬との相互作用に注意する
納豆に含まれるビタミンK2は、抗凝固薬の「ワーファリン」の効果を弱めてしまう可能性があります。この薬を服用している場合は、納豆を食べる前に医師に相談してください。
アレルギーに注意する
大豆アレルギーの人は、絶対に納豆を食べるのを避けましょう。アレルギーの人がアレルゲンとなる物質を口にした場合、皮膚のかゆみや発疹、口の中がイガイガするなどの違和感、のどが絞まるような感じなどの症状があります。
まとめ
納豆は栄養価が高く健康に良い食品ですが、アレルギーや薬との相互作用などには注意が必要です。注意点を守って、健康的な毎日のためにいつもの食生活に取り入れてみてください。









