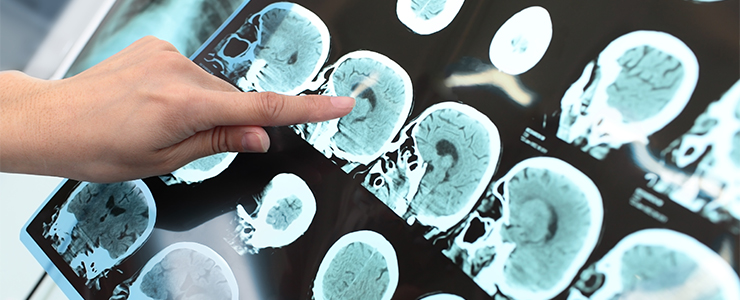コラーゲンの3つの役割。不足すると起きる体の不調も解説

コラーゲンにはどんな役割があるの?
コラーゲンが不足するとどんなことが起きるの?
このように疑問を感じることがあるかもしれません。
コラーゲンは体のさまざまな場所に存在していて、皮膚に弾力を与えたり、丈夫な骨をつくったりしていて体に欠かせないものです。
本記事では、コラーゲンの役割や不足したときに起きる体の不調などを解説していますので、コラーゲンについての理解を深めていきましょう。
コラーゲンとは?

コラーゲンとはたんぱく質の一種のことで、体全体のたんぱく質のうち約30%がコラーゲンです。体内では29種類のコラーゲンが発見されており、発見順にⅠ型、Ⅱ型…と分類されています。
コラーゲンは三重のらせん構造になっており、安定していて、しなやかであることが特徴です。皮膚・骨・軟骨・血管・腱・角膜・歯など、体の部位ごとに存在していて、それぞれが大切な役割を担っています。
コラーゲンの3つの役割

コラーゲンには主に以下3つの役割があります。
皮膚に弾力を与える
丈夫な骨をつくる
間接の動きをなめらかにする
皮膚に弾力を与える
コラーゲンは外の衝撃から皮膚を保護し、さらには皮膚の弾力を保つ役割があります。コラーゲンのうち約40%は皮膚に存在しており、これにより皮膚を引っ張っても元に戻るしなやかさがあるのです。
丈夫な骨をつくる
骨を構成する成分の半分はコラーゲンでできています。骨はコラーゲンを土台としており、コラーゲンが劣化すると骨の質が低下することに。コラーゲンが不足すると、乾燥したヘチマのようにスカスカの骨になるため、骨折しやすくなります。
関節の動きをなめらかにする
関節には、動きをなめらかにするクッション剤の役割をしている「軟骨」があります。
軟骨の主な成分はコラーゲンでできており、これにより関節の曲げ伸ばしがスムーズにできるのです。
軟骨は加齢や肥満などですり減ることがわかっており、すり減ると骨と骨がぶつかって、痛みや炎症などを引き起こします。
コラーゲン不足で起きる体調不良

コラーゲンが不足すると起きる体の不調には以下のものがあります。
骨粗しょう症
眼精疲労
皮膚のたるみやしわ
それぞれ解説していきます。
骨粗しょう症
骨粗しょう症は骨の密度が低下して起きる病気です。骨をつくる成分のコラーゲンが不足すると、骨の強度も低下することがわかっています。
眼精疲労
コラーゲンが不足すると眼が疲れやすくなり、眼の痛みや見えづらさなどの症状があらわれます。眼の角膜や水晶体などはコラーゲンが含まれており、ピント調節などに役立っています。そのため、コラーゲンが不足するとうまくピントが合わなくなり眼精疲労になってしまうのです。
皮膚のたるみやしわ
コラーゲンには皮膚のはりや弾力を保つ役割がありますので、不足すると、たるみやしわの原因になります。皮膚は、表皮・真皮・皮下組織に分かれていて、このうち、皮膚を支えるベースとなっているのは真皮です。真皮全体の約70%はコラーゲンなので、不足すると、真皮の上に位置する表皮を支えきれずに、皮膚がたるんだりしわになったりします。
コラーゲンの摂り方

コラーゲンの量は、普段からバランスの良い食事をしていればとくに問題はありませんが、食事を抜いたり偏った食事をしたりしていると不足してしまいます。そのため、たんぱく質を含むバランスの良い食事を摂ることが大切です。
コラーゲンを多く含む食品には、鶏手羽先・鶏皮・軟骨・牛すじ・豚足・皮ありの鮭・うなぎなどがあります。また、摂取後に体内でコラーゲンを生成するにはビタミンCや鉄分が必要になりますので、合わせて摂取するように心がけましょう。
まとめ
コラーゲンは私たちの体に欠かせない存在ですが、加齢などで不足したり劣化したりします。不足したコラーゲンを補うためにも、バランスの良い食事を心がけて、健康的な生活を送りたいものですね。