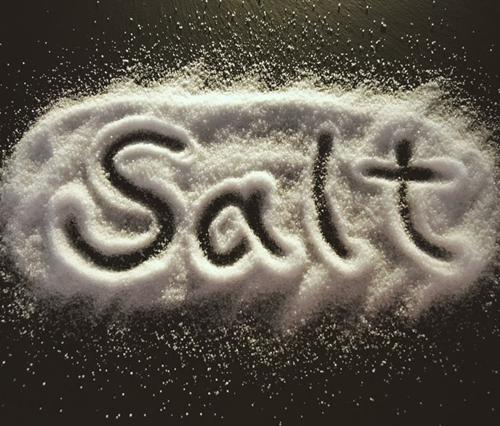音楽で心が軽くなる?メンタルヘルスと音楽の意外な関係

「気持ちが落ち込んだときに音楽を聴いたら、少し心が軽くなった」という経験をした人も多いのではないでしょうか。
音楽には、私たちの心と脳に直接働きかけ、感情を調整する力があります。
近年では、医療や心理の分野でも「音楽療法」として注目されており、セルフケアの手段としても広がりを見せています。
本記事では、音楽が心に与える影響や、科学的な背景、気分に合わせた選び方などを紹介します。
音楽が心に与える影響とは

音楽を聴いて「癒される」と感じるのは、脳内でさまざまな変化が起きているからです。音楽は「脳の報酬系」と呼ばれる領域を刺激し、やる気や快感を引き出すドーパミンを分泌させます。
ドーパミンは、心地良さやモチベーション向上に関係しています。音楽によって脳が「ご褒美」を感じることで、気分を上向きにする働きがあるのです。
また、音楽は感情と強く結びつく特徴があります。たとえば、失恋のときに聴いた曲を後から聴くと、その時の気持ちがよみがえることがあります。これは、音楽が記憶や感情とリンクして、心に深く刻まれるためです。
さらに、穏やかな音楽を聴くと、リラックス時に現れるアルファ波が脳内で増加し、自律神経のバランスを整えます。これにより、緊張がほぐれ、ストレスの緩和や安眠につながります。
科学的に見た「音楽療法」

音楽は、感覚的に楽しむものというだけでなく、医療や福祉の現場でも「音楽療法」として利用されています。
音楽療法とは、音楽を使って心身の回復を支援するアプローチのことです。うつ病や不安障害、認知症、発達障害、終末期医療など、さまざまな分野で実践されています。
たとえば、認知症の高齢者に対しては、昔親しんだ音楽を聴かせる「回想法」が有効です。懐かしい曲を通じて記憶が刺激され、感情が豊かに表現されることがあります。
緩和ケアでは、音楽を通じて痛みや不安を和らげ、穏やかな時間を過ごすための支援として用いられています。
音楽療法は、聴くだけでなく、歌う・演奏するといった能動的な関わりも重視されます。
声を出すことや楽器を鳴らすことで、オキシトシンと呼ばれる幸福ホルモンが分泌され、安心感や連帯感が高まることが知られています。
気分に合わせた音楽を選ぶコツ
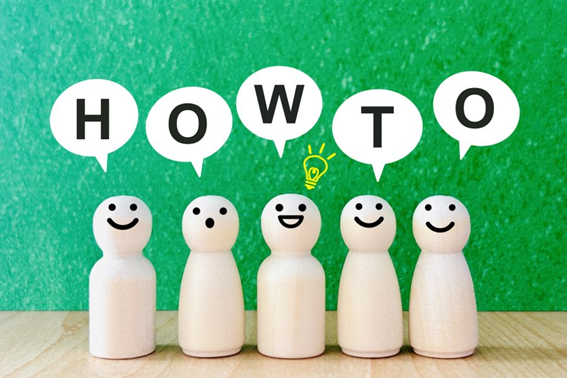
気分が落ち込んでいるとき、「元気な曲を聴こう!」と思うことはありませんか?
しかし、心が疲れているときに明るすぎる曲を聴くと、心と音楽との「温度差」で、かえって孤独や違和感を感じてしまうこともあります。
そのため、まずは今の気持ちに寄り添うような音楽を選ぶことが大切です。
たとえば、悲しいときはゆったりしたバラードで気持ちを落ち着け、少しずつテンポのある曲にシフトしていく。
このように、気分の変化に合わせて段階的に音楽を変えていくのもひとつの方法です。
また、自分だけの「気分別プレイリスト」を作っておくのもおすすめです。
朝の支度中、通勤時間、寝る前のリラックスタイムなど、シーンに応じた音楽を用意しておくことで、生活のリズムが整いやすくなります。
まとめ
音楽は、言葉にできない感情にそっと寄り添い、心の内側をやさしく整えてくれます。
これは、音楽により、セロトニンやオキシトシンなどの神経伝達物質が活性化することで、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分を穏やかにしてくれるからです。
ただし、どのような音楽が心に響くかは人それぞれです。無理に元気を出そうとせず、まずは今の気持ちを受け止めてくれる音楽を選んでみてください。
音楽は、静かに、でも確かに、私たちの心を支えてくれる力をもっています。日々のセルフケアのひとつとして、心地良いと思える音楽を、生活の中に取り入れてみましょう。