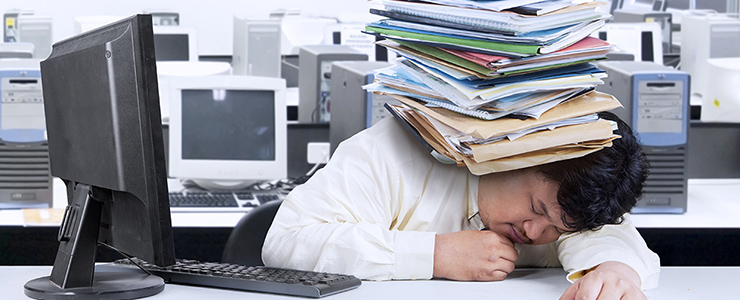寝起きにむくむのはなぜ?考えられる原因とすぐできる対策

寝起きに顔や手がむくんで、「何が原因だろう」と疑問に思ったことがありませんか?
寝起きのむくみには、体内の水分バランスや血流の状態、生活習慣などが関係しています。ほとんどは一時的なむくみですが、なかには病気のサインという可能性もあるため注意が必要です。
なぜ寝起きはむくみやすいのか?

寝起きにむくみを感じやすい原因は、以下のように体の仕組みや生活習慣による要因が重なっています。
重力と水分の分布
成人の体は約60%が水分でできています。日中は立ったり座ったりすることが多いため、重力の影響で体内の水分は下半身にたまりやすくなります。
一方、横になって寝ている間は、水分が顔や手を含めた全身に均一に広がるため、寝起き直後は顔が腫れぼったく感じたり指が動かしづらくなったりします。
血流やリンパの停滞
同じ姿勢で長時間過ごすと循環が滞り、特定の部位にむくみが出やすくなります。特に、睡眠中はほとんど体を動かさないため、血流やリンパの流れがゆるやかになりがちです。さらに、うつ伏せや横向きの状態で手を枕や体の下に入れると、継続的に手が圧迫され、起床時にむくみを感じやすくなります。
塩分やアルコールの摂取
塩分の多い料理やアルコール摂取は、寝起きにむくんでしまう原因のひとつです。塩分は、体が濃度を下げようとして水分をため込みます。アルコールは血管を拡張させたり、一時的な脱水のあとに体が水分を保持しようとするためむくみを引き起こします。
運動不足や冷え
筋肉には、血液を心臓に戻すポンプの役割があります。運動不足や冷えにより筋肉の働きが弱まると、余分な水分が滞り、むくみやすくなります。
ホルモンや体質の影響
女性は、ホルモンバランスの変化で水分をため込みやすい時期があります。体質的にむくみやすい人もおり、寝起きに症状が出やすい傾向にあります。
むくみやすい部位と症状

寝起きのむくみは、特定の部位に現れやすいのが特徴です。
顔:まぶたや頬が腫れぼったくなる
手:指輪がきつく感じる、指が動かしにくい
足:朝は軽くなるものの、循環が悪いと寝起きもむくむ
これらのむくみは、多くの場合が体を動かすうちに自然に引いていきます。
寝起きのむくみを解消する方法

朝のむくみは、少しの工夫で軽くすることもできます。
ストレッチや軽い運動をする
ラジオ体操や散歩をすると、血流が促され余分な水分が流れやすくなります。腕を大きく回したり、手をグーパーしたりするだけでも効果があります。
白湯や常温の水を飲む
寝起きは体が脱水状態になるため、水分補給が大切です。このとき、冷水ではなく、白湯や常温水を飲むと内臓が温まり、代謝もアップしてむくみ解消につながります。
冷水とぬるま湯の交互洗顔・手洗い
顔や手を冷水とぬるま湯で交互に洗うと血管が収縮と拡張を繰り返すため、血流やリンパの流れが良くなり、むくみがすっきりします。
枕の高さを調整する
低すぎる枕で寝ると顔に水分が集まりやすくなります。そのため、やや高めの枕を使うことで水分が下がりやすくなり、翌朝の顔のむくみを予防できます。
塩分・アルコールを控える
前日の食事を見直すことも重要です。塩分を控えめにしたり、飲酒を減らすことで、翌朝のむくみはかなり軽減できます。
注意が必要なむくみとは?

寝起きだけでなく、日中もむくみが続く場合や以下のような特徴があるときは注意しなければなりません。
むくみが片側だけに強く出る
押すと跡が残ってなかなか戻らない
しびれや痛みを伴う
顔や手足だけでなく全身にむくみが出る
これらの症状は、腎臓や心臓、甲状腺などの病気が関係していることもあります。むくみが長引く、悪化するなど不安がある場合は、早めに医療機関を受診してください。
まとめ
寝起きに顔や手がむくむのは、重力による水分の分布や寝姿勢、食生活など日常的な要因による一時的なものが多いです。ストレッチや水分補給、冷水とぬるま湯の交互洗顔などの工夫で、すぐに解消できることもあります。
ただし、むくみが長引いたり、片側だけ強く出たりする場合は病気のサインかもしれません。生活習慣を見直すとともに、必要に応じて医療機関を受診し、自分の体からのサインを見逃さないようにしましょう。