疲れているのに眠れないのはなぜ?原因と対処法を解説

「体は疲れているのに、布団に入ると眠れない……」。
疲れていると自然に眠くなると思われがちです。しかし実際は、疲労が強いほど眠れなくなることもあります。この症状を放置すると、一時的な不眠から慢性的な睡眠障害につながる可能性もあるため、注意しなければなりません。
本記事では、疲れているのに眠れない原因や、しっかりと眠るための対処法を解説します。
なぜ体は疲れているのに眠れないのか

「疲れている=眠れる」というイメージを持つ方は多いですが、必ずしもそうとは限りません。
人間の睡眠は、体の疲労だけでなく、脳や自律神経の働きにも大きく左右されます。
例えば、日中に強いストレスを受けると、脳が興奮状態のまま夜を迎えます。結果として「眠るためのスイッチ」を切り替えられず、体が疲れても眠れなくなってしまいます。
寝る直前のスマホ使用やカフェイン摂取なども、眠りに必要なホルモンである「メラトニン」の分泌を妨げ、眠気が起こりにくくなる原因のひとつです。
体が疲れているのに眠れない原因

疲労が強いのに眠れない場合、いくつかの要因が関係している可能性があります。ここでは代表的な4つの原因を解説します。
ストレス
精神的なストレスは、眠れなくなる原因の代表です。
ストレスは、交感神経を活発にして心拍数や血圧を上昇させるため、体や脳の緊張状態が解けず、布団に入っても眠りにつけません。
さらに「眠れないこと自体がストレス」となり、より悪循環に陥るケースもあります。
体内時計の乱れ
夜更かしや休日の寝だめなどで生活リズムが崩れると、睡眠やホルモン分泌のリズムを管理する「体内時計」が乱れ、眠りたい時間に自然な眠気が起きにくくなります。
特に、スマホやPCのブルーライトは、メラトニンの分泌を抑えてしまい、疲れているのに眠れない原因となります。
飲み物の作用
コーヒーや紅茶、エナジードリンクに含まれるカフェインは、覚醒作用が強く、摂取から6時間ほど体内に残るため、夕方以降に飲むと眠りを妨げます。
また、大量のアルコールは、眠りを浅くして夜中に目が覚めやすくなるため、摂取量に注意しましょう。
病気の影響
疲れているのに眠れない状態が長期間続く場合、病気が関係しているケースもあります。
代表的なものには、不眠症や睡眠時無呼吸症候群が挙げられます。また、更年期障害やうつ病などが睡眠に影響することもあります。
「毎日眠れない」「日中も強い眠気が続く」といった症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
しっかりと眠るための対処法
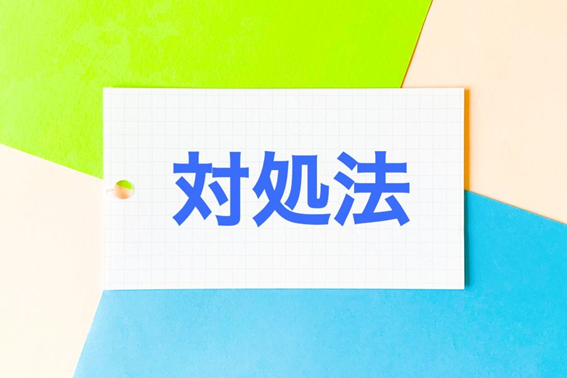
眠れない原因がわかれば、生活習慣を見直すことで改善できるケースも多くあります。ここでは今日から始められる対策を紹介します。
生活習慣を整える
毎日同じ時間に起きる、朝日を浴びる、適度な運動を取り入れるといった生活習慣は、体内時計を整える効果があります。
特に「同じ時間に起きる」ことがポイントで、休日でも起床時間を大きくずらさないように心がけましょう。
寝る前にリラックスする
眠る前は、心身をリラックスさせることが大切です。
ぬるめのお湯で入浴したり、深呼吸や軽いストレッチを行うと眠りにつきやすくなります。
寝る直前まで仕事や考え事をしていると脳が休まらないため、就寝前はリラックスタイムを確保しましょう。
スマホやパソコンと距離を取る
ブルーライトはメラトニン分泌を妨げ、眠気を遠ざけるため、就寝1時間前からはスマホやPCの使用を控えましょう。難しい場合はナイトモードを活用するのもおすすめです。
眠れないときは気分転換する
布団で「早く眠らないと!」と焦ると、余計に眠れなくなるものです。
20分以上眠れないときは一度布団から出て、軽く読書や瞑想、深呼吸などで気分転換しましょう。心が落ち着くと、眠りにつきやすくなります。
まとめ
疲れているのに眠れないのは、ストレスや生活リズムの乱れなど、心身のバランスが崩れているサインです。
生活習慣の見直しや寝る前のリラックス習慣を取り入れることで、多くの場合は改善が期待できます。
ただし、症状が長期間続いたり、日常生活に支障が出たりする場合は、不眠症などの病気が隠れている可能性もあります。早めに医療機関に相談し、適切な治療を受けましょう。
しっかり眠ることは、疲労回復だけでなく心の健康にもつながります。今日から少しずつ、眠りやすい環境づくりを始めてみてください。









