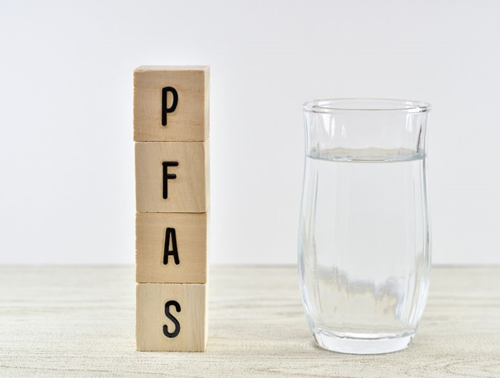夏でも冷え性に悩む人必見!原因と改善法をわかりやすく解説

「夏なのに手足が冷えてつらい」「冷房の効いた室内で体がだるくなる」そんな不調に悩んでいませんか?
暑い季節でも、冷え性は多くの人が抱える悩みのひとつです。特に女性に多いとされる夏の冷え性は、放っておくと頭痛や不眠、胃腸の不調などさまざまなトラブルを引き起こす原因になります。
本記事では、夏の冷え性が起こる理由とその改善法について、わかりやすく解説します。
夏でも冷え性になる5つの理由

夏なのに冷え性になる主な原因は、以下の通りです。
自分はどれが原因なのかを考えながら確認していきましょう。
1.冷房による温度差と自律神経の乱れ
夏の冷え性の最大の要因は、外の暑さと室内の冷房による温度差です。
人間の体は、外気温に合わせて体温を調節するために自律神経が働いています。
しかし、急激な温度差にさらされ続けると、自律神経が乱れ、体温調節がうまくできなくなり、手足の末端から冷えていきます。
2.冷たい飲食物の摂りすぎ
気温が高い日は、アイスや冷たい飲み物が手放せなくなりがちです。
冷たい飲食物ばかり摂っていると、内臓が冷え、全身の血の巡りが悪くなり、末端の冷えが強く感じられるようになります。
3.運動不足と筋肉量の低下
筋肉には「熱を生み出すエンジン」のような役割があります。そのため、運動不足や筋肉量の低下は、体が熱を作り出せなくなる原因のひとつです。デスクワーク中心の生活や運動習慣のない人は、冷えを感じやすい傾向にあります。
4.ストレス・生活習慣の乱れ
強いストレスや不規則な生活は、自律神経のバランスを崩す一因になります。睡眠不足や夜型の生活を続けると、体温調節のリズムが乱れ、冷えを招きやすくなります。
5.食事量の減少や栄養不足
夏は食欲が落ちやすく食事量が減るため、エネルギー不足となり、体が熱を作るための材料が不足します。特に、鉄分やビタミン類の不足は、血流の悪化につながるため注意が必要です。
冷え性が引き起こす夏の不調

夏の冷え性を放置すると、以下のような不調が現れます。
• 手足の冷えやしびれ
• 肩こりや腰痛
• 頭痛、めまい、吐き気
• 胃腸の不調(下痢・便秘・食欲不振)
• むくみやだるさ
• 寝つきの悪さ、不眠
これらはすべて、体の巡りの悪さや自律神経の乱れが引き起こす症状です。「夏バテかな?」と思っていた不調も、実は冷えが根本にある場合もあります。
夏の冷えを防ぐためにできること

冷え性対策は、日常のちょっとした工夫で始められます。以下のセルフケア法を、生活の中に取り入れてみましょう。
冷房対策をする
室内外の温度差は7℃以内が理想です。設定温度を少し高めにしたり、薄手のカーディガンやレッグウォーマー、ストールを常に持ち歩いたりして調節するのがおすすめです。
特に、首・手首・足首は太い血管が皮膚の近くを通っているため、冷やさないように心がけましょう。
温かい飲食物を摂る
暑い日でも、常温や温かい食べ物・飲み物を意識的に取り入れましょう。内臓が温まることで血管が拡張して、血流が全身に巡りやすくなります。
入浴で体を温める
暑いからとシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、血流が促進され、冷えの改善につながります。
運動を習慣にする
ストレッチや軽いウォーキング、スクワットなどの筋トレを日常に取り入れましょう。筋肉量が増えると体が熱を作りやすくなり、冷えにくくなります。
食事で巡りをサポートする
体を温める食材(ショウガ、にんにく、根菜類、発酵食品など)を意識して摂りましょう。また、鉄分やビタミンE、たんぱく質を意識的に摂取することで、血流がよくなり、冷え性改善に役立ちます。
自律神経を整える生活リズム
起床・就寝の時間を整え、十分な睡眠とバランスの取れた生活リズムを意識することで、自律神経が安定します。ストレス対策として、深呼吸や軽い瞑想も効果的です。
まとめ
夏の冷え性は、さまざまな体の不調を引き起こすリスクになります。
冷え性の原因は、冷房による室内外の温度差や冷たい飲食物などで、自律神経が乱れ、体温調節がうまくいかなくなることにあります。
しかし、生活習慣を見直すことで、十分に予防や改善が可能です。羽織りものを持ち歩いたり、運動や食事に気を配ったりするなど、できることから始めてみましょう。
「暑いのに冷える」という矛盾した不調を感じたら、それは体からのサインです。
夏こそ、体を温める習慣で、健康的な毎日を手に入れましょう。