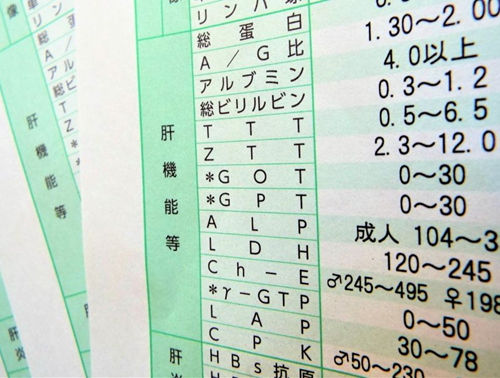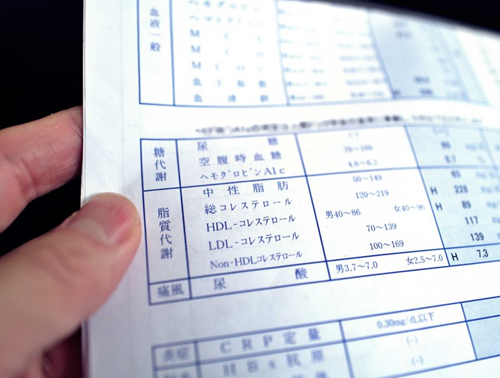和食はうつ病予防に効果的?心の健康を支える日本の食文化

忙しい日々のなかで、気分が落ち込んだり、やる気が出なかったりすることはありませんか?
近年、食事と心の健康との深い関係が注目されており、「和食」がうつ病の予防や改善に役立つ可能性があることも明らかになってきました。
発酵食品や魚、野菜中心の和食が、どのようにメンタルヘルスを支えるのかを見ていきましょう。
うつ病とは?主な原因と症状

うつ病は、長期間にわたり気分の落ち込みや意欲の低下が続く精神疾患です。
単なる「気分が沈む」状態とは異なり、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンの分泌異常が関与しています。
主な症状は、憂うつ感、興味の喪失、睡眠障害、食欲不振、集中力の低下、自己否定的な思考などです。
発症の要因はさまざまで、心理的ストレスや人間関係の悩みに加え、生活習慣の乱れや栄養不足も無関係ではありません。
近年では、脳と腸が密接に関わる「腸脳相関」の視点から、腸内環境の状態がメンタルヘルスに与える影響にも注目が集まっています。
うつ病と食事の関係

私たちの心と体は、毎日の食事によってつくられていると言っても過言ではありません。
なかでも、神経の働きに関わるアミノ酸やビタミンB群、鉄、亜鉛といった栄養素は、心の安定に大きく関わる大切な要素です。
たとえば「幸せホルモン」として知られるセロトニンは、トリプトファンというアミノ酸からつくられます。その過程では、ビタミンB6やマグネシウムなどの栄養素も重要な役割を担っています。
このように、日々の食事は心の健康を支える基盤となります。加工食品の摂りすぎや糖質に偏った食生活は腸内環境の乱れにつながり、気分の落ち込みや不調を引き起こす一因となることもあるのです。
和食がうつ病予防に役立つ理由

和食は、世界的にも健康的な食文化として評価されています。実際に、昔ながらの日本食をベースにした食生活を送る人ほど、うつ病の発症率が低いという研究結果も報告されています。
発酵食品が腸を整える
味噌、納豆、漬物などの発酵食品は、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあります。腸内で生成されるセロトニンは、脳にもよい影響を与えるとされており、発酵食品の摂取がストレス軽減や不安感の緩和につながります。
青魚のDHA・EPAが脳をサポートする
和食に欠かせない魚料理、特にサバやイワシなどの青魚に多く含まれるDHA・EPAには、抗炎症作用や脳機能の維持効果があります。これらは、うつ病患者の脳内で減少していることが確認されており、積極的に摂取することで症状の改善や予防に役立つと考えられています。
野菜・海藻・豆類が神経を安定させる
和食では、旬の野菜や豆腐、わかめなどがよく使われます。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、脳の正常な働きや神経の安定に欠かせません。特に、葉酸は神経伝達物質の合成に必要であり、不足すると抑うつ症状が現れやすくなるとされています。
和食を取り入れた生活習慣のすすめ

和食が心の健康によいとはいえ、毎日きちんとした和食を準備するのは難しいと感じる方も多いと思います。
そんなときは、少しだけ意識を変えてみましょう。
たとえば、朝ごはんに納豆ごはんと味噌汁をプラスするだけでも、腸と心によい影響を与えます。
コンビニを利用する場合でも、焼き魚のお弁当や海藻サラダ、味噌汁などを選ぶと、手軽に和食のエッセンスを取り入れられます。
また、「早寝早起き」「よく噛んで食べる」「できるだけ1日3食」といった基本的な生活習慣を整えることも、心の安定には欠かせません。
和食の特徴である「ゆっくり味わう食事」は、マインドフルネス(今ここに意識を向ける)とも通じる部分があり、ストレス軽減にもつながります。
まとめ
和食は、日本人の身体に合った栄養バランスを持つだけでなく、心の健康にも寄与する食文化です。
発酵食品や魚、野菜を中心とした食事は、うつ病の予防や改善にも効果が期待されています。腸内環境や神経伝達物質の生成を支える和食は、まさに「心のサプリメント」です。
忙しい日々のなかでも、少しずつ和食を取り入れた食習慣を意識すると、心が少しずつ軽くなるかもしれません。