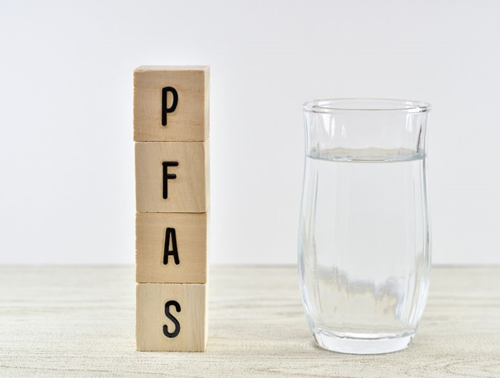血糖値スパイクとは?放置で糖尿病リスクが高まるワケ

健康診断で「血糖値は正常」といわれている人でも、食後だけ血糖値が急上昇することがあります。これは、「血糖値スパイク」と呼ばれ、放置すると、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞など、命に関わる病気につながる危険性があります。
この記事では、血糖値スパイクとは何なのか、また、血糖値スパイクを放置した際のリスクにはどのようなものがあるのかについてわかりやすく解説します。
血糖値スパイクとは?

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急激に下がる現象のことで、医学的には「食後高血糖」と呼ばれます。
私たちが主食として食べている炭水化物は、体内で糖に分解されて血液中に取り込まれます。通常は、膵臓から分泌されるインスリンが働くため、血糖値はゆるやかに下降します。しかし、一度に多くの糖質を摂取したり、血糖値の上昇を緩やかにする野菜が不足したりすると、血糖値が一気に上昇してしまいます。
これにより、体が慌てて大量のインスリンを分泌し、血糖値を下げようとするため、血糖値が急降下し、体がエネルギー不足だと勘違いしてしまうのです。
特に、丼物や菓子パンなど糖質中心の食事や早食い、運動不足や睡眠不足などが重なると、血糖値スパイクが起きやすくなります。
血糖値スパイクの症状と放置するリスク

血糖値スパイクは、一見するとただの「食後の眠気」や「だるさ」に見えることがあります。
しかし、次のような症状が繰り返し起きる場合は要注意です。
食後に強い眠気やだるさを感じる
仕事や勉強中に集中力が低下する
食後しばらくして強い空腹感が出る
甘いものが無性に欲しくなる
気分が不安定になり、イライラしやすい
これらの症状は、血糖値の急降下による「脳のエネルギー不足」が原因で起きている可能性があります。
血糖値スパイクの症状
血糖値スパイクを放置すると、糖尿病を発症するリスクが高まります。
繰り返し高血糖になると、膵臓が疲れてインスリンを十分に分泌できなくなります。さらに、体がインスリンをうまく使えなくなる「インスリン抵抗性」が進み、血糖値が下がりにくくなります。
こうして、最初は食後だけ高血糖だった状態が、やがて空腹時も血糖値が高い状態へと進行し、糖尿病を発症してしまうのです。
血糖値スパイクを放置するリスク
糖尿病になると、次のような合併症が起きる危険性があります。
動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞:血管が傷つき、命に関わる病気を引き起こす。
糖尿病網膜症:視力が低下し、最悪の場合は失明につながる。
糖尿病腎症:腎臓の機能が低下し、人工透析が必要になるケースも。
このように、血糖値スパイクは一時的な不調だけでなく、将来の重大な病気の引き金にもなるため、早めの対策が重要です。
血糖値スパイクを防ぐ食事の工夫と生活習慣

血糖値スパイクは、日々のちょっとした工夫で予防できます。ここでは、食事の工夫と生活習慣の見直しに分けて、今日から始められる対策を解説します。
食事の工夫
1. 食べる順番を意識する
2. 主食を低GI食品に置き換える
3. よく噛んでゆっくり食べる
野菜 → たんぱく質 → 炭水化物の順になるように食べる順番を意識すると、血糖値の上昇が緩やかになります。また、白米より玄米、うどんよりそば、食パンより全粒粉パンなど、血糖値が上がりにくい食品を選びましょう。
さらに、急な血糖値上昇を防ぐためには、ひと口30回を目安に噛んで食べるのがおすすめです。
生活習慣の見直し
1. 食後に10分程度ウォーキングをする
2. 睡眠時間をしっかりと確保する
3. ストレスをため込まないようにする
食後に軽く歩くことで、筋肉がブドウ糖をエネルギーとして使用するため、血糖値が下がりやすくなります。食後30分以内を目安に少し息が上がる程度の強度で取り組んでみましょう。
また、睡眠時間は、7時間前後を目安に確保します。睡眠不足になると、血糖値をコントロールするホルモンの働きを妨げてしまう原因となります。そして、強いストレスは、血糖値を上げるホルモンを分泌させてしまいます。リラックスできる時間を意識的に作ることが、血糖値スパイクを防ぐうえでも大切です。
まとめ
血糖値スパイクは、食後に急激に血糖値が上がり、その後急激に下がる現象です。
「食後に眠くなる」「甘いものがやめられない」といった日常の不調も、実は血糖値スパイクが原因かもしれません。
放置すると糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞など、命に関わる病気を招く恐れがあるため、早めの対策が必要です。
まずは、食べる順番を変える、食後に軽く体を動かすなど、簡単なことから始めてみましょう。